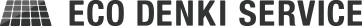


屋根が大きい住居では、一般家屋でも産業用規模(10kW以上)の太陽光発電を導入可能です。
そのため、太陽光発電を自宅に設置する際に、住宅用と産業用のどちらにするか悩まれる方もいるのではないでしょうか。
今回は、産業用に区分される10kW以上の太陽光発電についてどのようなメリットがあるかまとめました。
ぜひ参考にしてみてください。
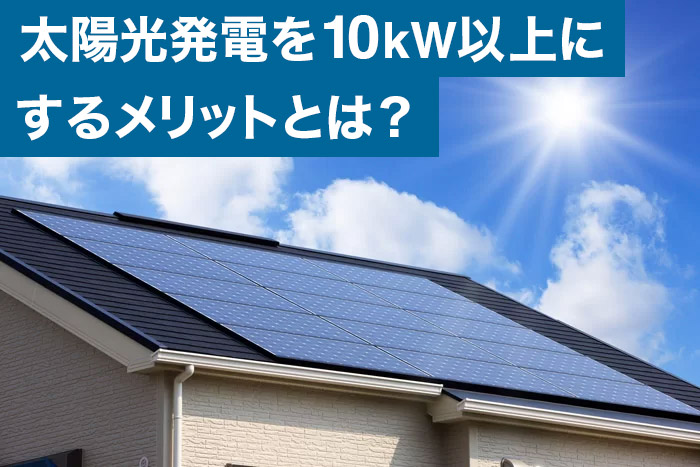
再生可能エネルギーで注目される太陽光発電ですが、出力容量で用途が異なることはご存じでしょうか?
ここでは、10kW以上の太陽光発電によるメリットや、売電収入などについて解説していきます。

「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」という、再生可能エネルギーで発電した電気を電力会社が一定価格で一定期間買い取ることを国が約束する制度があります。
固定価格で買い取ってもらえる年数は、10kw未満が10年間、10kW以上の場合には20年まで延長されるため、これが10kW以上の太陽光発電を導入するメリットといえるでしょう。
しかし、10kW以上の太陽光発電の場合1kWあたりの固定価格は10〜12円と、10kW未満よりも低く設定されているため注意が必要です。
また、太陽光発電の電力は年間で68.8%が売電、31.2%が自家消費に割り当てられています。
太陽光発電システムの容量が増えることで約30%にあたる自家消費の電力量も増加し、電気代の削減ができるでしょう。
そして、災害時に電力会社から電力の供給が止まってしまったとしても、大容量の太陽光発電システムがあれば一定期間は安心して電力を活用できます。
このように10kW以上の太陽光発電のメリットは多岐にわたります。

売電収入とは、発電設備によって発電した電力を、電力会社に対して売却する際に得られる収入を指します。
10kW以上の太陽光発電を設置した場合、1kWあたりの年間発電量が1,000kWh・発電される電力の割合が68.8%・屋根設置による電力の固定買取価格が1kWh12円であるケースでは、年間約82,000円の売電収入を得ることができます。
前述の通り、10kW以上の太陽光発電は20年間固定買取価格で売却することができるため、長期的に売電収入を得ることが可能といえるでしょう。

10kW以上の太陽光発電の導入を検討している方の中には、10kW未満の太陽光発電との具体的な違いについて、気になる方もいらっしゃるでしょう。
ここでは、発電量と設置面積の違い、システムと設備の比較、家庭用と産業用の違いについて解説します。

1kWあたりの年間発電量は、約1,000kWhが目安です。
一般的な家庭の場合、太陽光発電システムの発電容量は3〜5kW程度であるため、家庭用の1日の発電量はおよそ8.1〜13.5kWhです。
それに対し、10kW発電できる太陽光発電設備では、1日の発電量は約27kWhとなります。
屋根の方角と太陽光パネルの角度は発電量に直接的に関わってきます。
太陽光パネルを設置する屋根の包囲は南が最適と言われており、屋根の角度は30度前後が理想的です。
また、太陽光パネル1枚あたりの発電量は決まっているため、枚数および設置面積が発電量に影響を与えます。
なお、太陽光1枚あたりの発電量の目安は、70~250Wです。

一般的に10kW未満の住宅用太陽光発電は、屋根やカーポートなどに太陽光パネルを設置することが多いです。
一方で10kW以上の産業用太陽光発電は、工場・ビルのような広い屋根や壁、または広大な土地に太陽光パネルを設置するケースがほとんどです。
住宅用と産業用では選択する太陽光パネルにも違いがあります。
一般的な家屋の屋根に太陽光パネルを設置する場合、シリコン系の単結晶パネルが選択されることが多いです。
理由はシリコン系の単結晶パネルは発電効率が高く、設置できる枚数に限りがある住宅用に向いているからです。
産業用太陽光発電で多く使われているのが、シリコン系の多結晶パネルです。
多結晶パネルは単結晶パネルよりも発電効率が落ちるものの、パネルの値段が比較的安価なため、たくさんのパネルを必要とする産業用では初期費用を抑えるために選ばれるケースが多いです。

太陽光発電は、住宅用・産業用に分かれています。この違いは屋根に乗せる発電設備の出力容量の差で、出力容量が10kW未満なら住宅用、10kW以上なら産業用となります。
一般住宅でも10kW以上の太陽光発電を設置することで、産業用に区分されるのです。
産業用太陽光発電は、余剰売電と全量売電が選べることが最大の特徴であり、実際に使用するのが個人・事業者どちらでも問題ありません。

実際に10kW以上の太陽光発電を導入する際、設備にかかる費用としてはどのようなものがあるのでしょうか。
ここからは設置費用・価格相場・初期コストなどについてご紹介いたしますので、ぜひ参考にしてみてください。

太陽光発電システム設置費用内訳は、機器費用・工事費用の2種類です。
機器費用に含まれるものは太陽光パネル・パワーコンディショナ―・接続箱・ケーブル関係・架台があり、工事費用には電気工事・パネル設置工事・足場工事などがあります。
近年の住宅用太陽光発電システムの平均設置費用は新築で26.1万円/kW、既築で28.1万円/kWです。
しかし、2013年ごろは平均設置費用が40万円/kW程度必要だったため、右肩下がりで低減しています。
そして、産業用の太陽光発電1kWあたりの設置費用の相場は23.6万円とされているため、10kwでは236万円が設置費用の平均となるでしょう。
産業用・住宅用ともに設置費用が減少傾向にある要因としては、技術進歩による低コスト製造や大量生産による低価格化が考えられます。
太陽光発電の初期費用には、太陽光パネルやパワーコンディショナーなど必要な機器の購入代金、設置工事費用が含まれます。
10kW以上の太陽光発電の設置費用は、屋根設置・地上設置で異なり、屋根設置の設置費用の合計は22.3万円/kWです。
これを基にすると、初期コストは10kWで223万円、20kWで446万円、30kWで669万円となります。
そして、地上設置の設置費用の合計は、28万円/kWです。
10kWでは280万円、20kWで560万円、30kWで840万円となります。
初期費用を抑えるためには、補助金を利用する・PPAモデルを検討するなどがあります。
さまざまな場所に太陽光パネルが設置されていますが、太陽光発電の設置には場所によって向き不向きがあります。
太陽光発電設置に適した条件としては、日光を遮るものがない場所・傾斜のない場所・自然災害の影響を受けづらい場所が挙げられます。
太陽光パネルの設置場所として傾斜のある土地だと、基礎の安定した設置が難しく、土砂崩れのリスクも考えられます。
また、地盤の弱い土地の場合、台風や大雨の影響で土砂崩れが発生し、太陽光発電が崩壊してしまうというリスクが考えられるでしょう。
このような観点から、設置場所の選定は設置後の発電量に大きく影響するため、慎重に選ぶ必要があります。
10kw以上の太陽光発電に投資するメリットは何でしょうか。
ここからは、FIT制度の活用や節税対策などについて解説いたします。
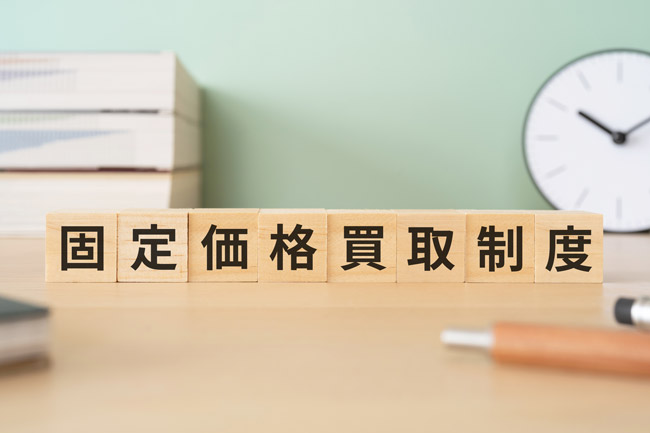
FIT制度とは、太陽光発電などの再生可能エネルギーを固定の価格で売却できる制度を指します。
電気の売却方法には、発電した電気を全て売ることができる「全量買取」と、自家消費を優先して余った電気を売る「余剰買取」があります。
余剰買取は、発電した電気を全て売電せずに、自家消費して余った電力を売電するという仕組みです。
対して全量売電は、太陽光発電によって発電したすべての電気を電力会社に売電する仕組みであり、発電設備の設置容量が50kW以上の設備が対象です。
ただし、ソーラーシェアリングに限り「災害時に電源として使用できること」「10年間の一時転用が認められる」という条件付きで、10kW以上50kW未満でも全量売電が認められています。
実際に、全量買取と余剰買取ではどちらの方がお得なのでしょうか。
買取金額は年々低下しているのに対し、ご家庭が電力会社から購入する電気料金の平均単価は上がっています。
このことから、発電した電気を売るよりも、蓄電池を設置して夜間の電気を購入しないで蓄電池の電気を自家消費する方がお得になるといえるでしょう。
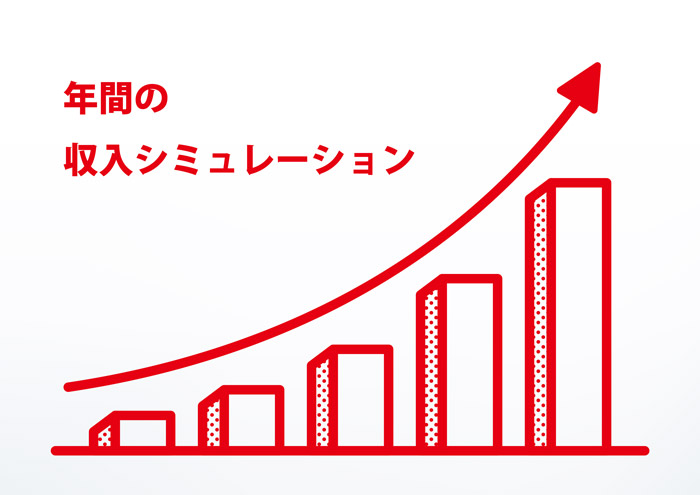
1日あたりの発電量は、1日の平均日射量×太陽光発電の出力×損失係数という計算式で確認することが可能です。
また、各メーカーのHPなどでもシミュレーションをすることができます。
太陽光発電は、お住まいの地域や設置する場所・傾斜・方角によっても、かなり発電量が変わってきます。
そのため、実際にどのような状態で設置可能か調べた上で施工会社やメーカーに問い合わせて、現実に近いシミュレーションを算出することをおすすめします。

自家消費型の太陽光発電の導入は、税額控除を受けられる場合があります。
「中小企業経営強化税制」上の中小企業に該当する場合は、自家消費型の太陽光発電を選択することで税額控除を受けることができるのです。
設備の取得にかかった費用のうち、一定の割合が法人税額から控除されます。
その他にも、設備の設置費を経費計上できる場合があったり、税制優遇制度を利用できる場合があったりするため、一度調べてみると良いでしょう。

10kW以上の太陽光発電を自家消費するためにはどのような方法があるのでしょうか。
自家消費のメリットや節電効果、蓄電池を取り入れた際の効果などについて解説します。
FIT法が改正され、50kW未満の発電設備は自家消費が前提となり、全量売電ができなくなりました。
自家消費が増えると、CO2の削減になる・電気料金の削減になる・災害時の非常用電源として使えるなどのメリットがあります。
このような法改正の背景としては、2020年のカーボンニュートラル宣言からCO2削減の取り組みが求められはじめたことが考えられます。
さらに、原油価格の高騰や世界情勢の緊迫化によって電気料金が高騰していること、自然災害への備えとして非常用電力が求められていることが原因といえるでしょう。
電気代は、「1時間あたりの消費電力×使用時間×料金単価」の計算式で求めることができます。
よく使う電化製品の電気代を算出し、自家発電により電力会社から購入する電力を減らして、電気代を削減しましょう。
蓄電池をうまく活用することで、 FIT終了後も売電から自家消費へシフトすることで電気代削減につなげられます。
また、化石燃料由来の電気をなるべく使わないことで、太陽光発電のみの暮らしよりもさらに環境負荷軽減に貢献することができるでしょう。
万一の非常時にも電気が使えるようになるなど、多くのメリットがあります。

10kw以上の太陽光発電を設置するためには、どのような申請手続きや方法があるのでしょうか。
ここからは、審査の流れや期間・メンテナンスなどについて見ていきましょう。
太陽光発電設置後、すぐに発電や売電はできません。そのため、事業計画認定申請を行ってFIT認定を受ける必要があります。
10kW以上と10kW未満の太陽光発電の設置ではそれぞれ必要な書類が異なります。
10kW以上の太陽光発電では、基本的に下記の書類が必要になります。
上記の書類を用意して電力会社に接続契約の申込をして、国へ事業計画認定申請をする流れになります。
審査の流れは、下記になります。
FIT制度の認定を受けるまでに、申請してから認定までの処理期間は3ヵ月ほどになります。
しかし、記載漏れなどの不備があった場合にはそれ以上の期間が必要となる場合があるでしょう。
2017年4月FIT改正後、従来50kW以上の産業用太陽光発電にのみに適用されていた「保守点検・メンテナンスの義務化」の適用が、ほとんどの発電設備において必須となりました。
太陽光発電システムの点検・メンテナンスを怠ると、発電効率の低下や故障などのリスクを高めるだけでなく、FIT認定取消など厳しい処分を受ける可能性があります。
メンテナンスにより、モジュールの劣化に伴い発熱が生じるケースや、固定部のゆるみや保護管の劣化など安全性に関わる問題を早期発見して対応することができます。

出力容量は大きくなるメリットはありますが、その分デメリットも生じます。
どのようなデメリットがあるか、どのように対策をすれば良いか解説します。
発電量が多くなればなるほど、導入費用が高くなるうえに設備も大きくなります。
そのため、導入コストやメンテナンス費用がかかります。
ローンでの購入も可能ですが、予想以上に発電量が少なくなるリスクや修理・交換費用が突然必要になることを考慮しましょう。
10kW以上の太陽光発電はソーラーパネルの枚数が多いため、それだけ多くの設置スペースが必要です。
空き地に太陽光発電を設置する場合は広い土地、屋根に設置する場合は大きな屋根が必要になります。
屋根の面積が足りない場合は物置やカーポートなどを利用するのも1つの方法ですが、配線工事や取付工事などに別途費用がかかるため、コストのトータルは上がってしまいます。
出力10kW以上50kW未満の太陽光発電を設置する場合は、電気主任技術者の選任や保安規程の届出は免除されます。
しかし、設備の使用の開始前に経済産業省令で定める基礎情報の届出を行うこと、及び技術基準に適合することを自ら確認し、その結果の届出を行うことが義務化されました。
また、経済産業省令で定める技術基準に適合するように所有する設備を維持する義務があり、職員による立入検査を受けることがあります。
このように手続きも複雑になり、準備する書類も多くなるため、デメリットととらえる方も多いでしょう。

10kW以上の発電設備の技術とトレンドにはどのようなものがあるでしょうか。
ここでは、最新のソーラーパネル技術や太陽電池の種類、発電効率を高める技術について解説します。
太陽光パネルは、大きく分けて「シリコン系」「化合物系」「有機物系」の3種類ですが、ペロブスカイトと呼ばれる結晶構造の材料を用いた新しいタイプの太陽電池が注目を集めています。
材料を塗布や印刷でつくることができ、 ゆがみに強く軽量化も可能であり、製造コストを抑えることができることが理由として考えられます。
太陽電池にはたくさんの種類があります。
低コストなものから高性能なもの、フレキシブルなものやカラフルなものなど、性能も形態も様々です。
シリコン系・化合物系・有機系に分けることができ、最もメジャーなシリコン系は結晶シリコン太陽電池、アモルファスシリコン太陽電池などがあります。
単結晶シリコン太陽電池は、エネルギー変換効率が20%程度と高く、さらに耐久性に優れているのが特徴です。
それに対し多結晶シリコン太陽電池は、単結晶シリコン太陽電池と同等の耐久性を持ちながら、構造的な問題から変換効率はやや劣る傾向にあります。
しかし、単結晶シリコンと比較すると、製造コストを安価に抑えることが可能です。
他にも様々な種類があり、そのどれもが少しずつ改良され続けています。
太陽光発電の発電効率を高めるには、
などがあります。
発電効率を向上させるためには太陽光パネルの選定も慎重に行う必要があり、高品質で発電効率の高いパネルを選ぶことで発電量が多くなり、長期間にわたって安定した発電が期待できるでしょう。
また、屋根の形状やサイズに合わせてパネルを選択することも大切で、設置可能な面積を最大限に生かせるように考えましょう。

ここからは、10kw以上の太陽光発電を取り扱う企業やそのプランについてチェックしましょう。
それぞれの企業でコストやプランなどが異なりますので、導入前に確認することが大切です。
おすすめ企業として、「長州産業」「シャープ」「カナディアンソーラー」などが挙げられます。
長州産業は、国内で製造した品質の高い太陽光パネルが人気で、パネルと蓄電池メーカーを揃えて有効活用でき、ソーラーパネルの種類が多いことで人気を集めています。
シャープは、老舗で大手のソーラーパネルメーカーであり、パネルと蓄電池メーカーを揃えて有効活用できたり、新築でオール電化住宅ができたりする点が魅力です。
他にもたくさんのメーカーがありますのでぜひ調べてみてください。
太陽光発電の見積もりを取る際は、事前に十分な準備が必要です。
自宅の屋根の向きと面積、年間の電気使用量、設置場所の日陰状況などを事前に確認しておき、見積書の内容も入念にチェックする必要があります。
太陽光発電システムの見積もりが適正かどうかを判断するには、総額だけでなく1kWあたりの単価も確認することが重要です。
それぞれの企業で特徴や代表的な製品、太陽光パネルのタイプ・製品数・発電出力展開・変換効率・価格帯・付帯サービスが異なるため、細かく確認する必要があるでしょう。
自分のライフスタイルに合った最適な企業を探してみてください。
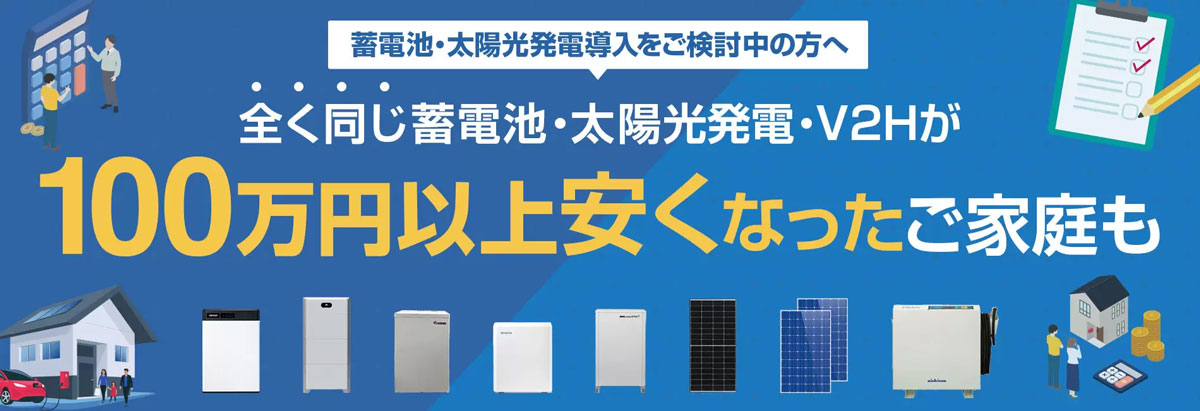
近年、様々な要因で高騰が続いている電気代ですが、お住いの住宅の屋根に太陽光発電を設置する事で自宅で発電を行い大幅に電気代をお安くする事が出来ます。
太陽光発電システムに合わせて、蓄電池を導入する事で自宅で発電した電力を貯めて効率的に使う事が可能になります。
エコ電気サービスでは、蓄電池と太陽光発電の導入のご相談・導入に伴うお見積りを無償で行っております。
お客様のご自宅に最適な機種、パネル枚数、メーカーなどをご提案させていただいております。
電気代の高騰対策として蓄電池と太陽光発電の導入をご検討の場合はエコ電気サービスまでお気軽にご相談下さいませ。
