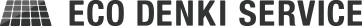

私たちは東証・名証上場の 株式会社東名 のグループ会社です
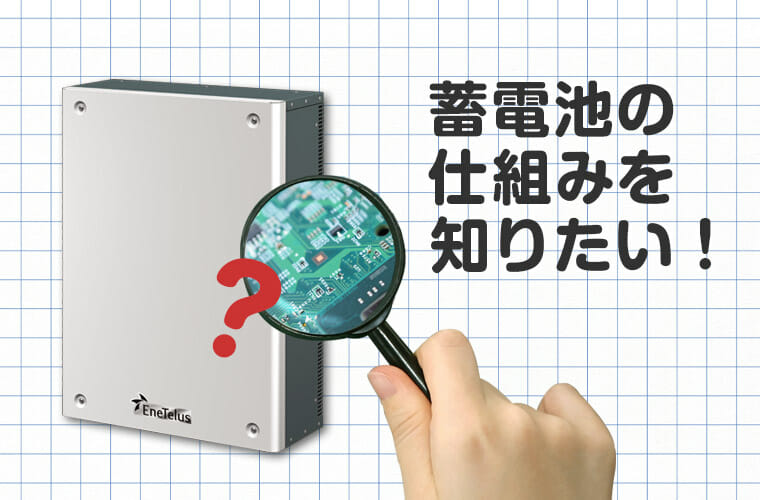
蓄電池の仕組みをご存知ですか?
太陽光発電や電気自動車が普及し始めた昨今、蓄電池の話題を耳にする機会も増えたことと思います。様々な話を聞くうちに、蓄電池のメリットやデメリットなども詳しくなられたのではないでしょうか。
しかしせっかく知識が増えても、そもそも蓄電池がどういうものなのか知らないことには、具体的に検討することは難しいですよね。
今回はそんな蓄電池の仕組みについて解説していきます。
蓄電池のメリット・デメリットについて詳しく知りたい方・おさらいしておきたい方は「蓄電池のメリット・デメリット まとめ」の記事をご参照ください。
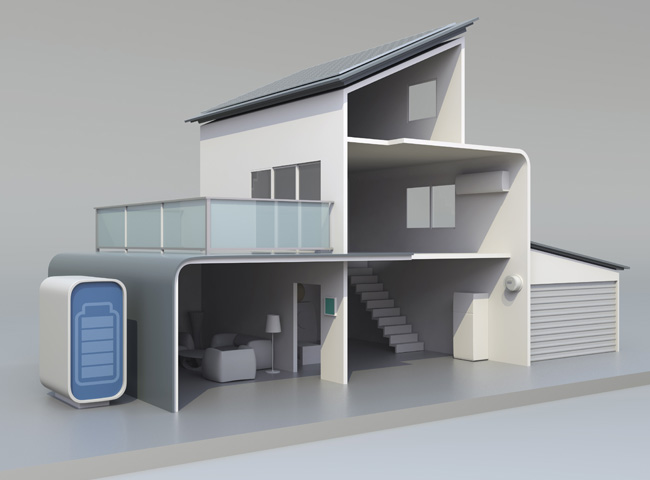
蓄電池とは電力会社から購入した電気や太陽光発電で発電した電気を充電し、貯めておくことができる設備です。
蓄電池に貯めた電気は昼間や夜間、停電時など必要な時に放電して使用できます。
特に太陽光発電やエコキュートと相性がよく、太陽光発電で発電した電気を貯めて夜間に使用したり、深夜の割安になった電気を貯めておいて、逆に電気代が割高になった昼間に使用するなどして活用可能です。
近年では太陽光発電の余剰電力買取制度(FIT)の期間が満了し売電単価が安くなることに加え、電気代の高騰も手伝って自家発電・自家消費に切り替えるために蓄電池を導入するご家庭が急増しています。
また、大容量の蓄電池であれば1日分以上の電気を貯められることから台風などの自然災害に伴う停電時の非常用電源としても人気です。
一部のハウスメーカーでは新築時に太陽光発電と一緒に蓄電池も設置できるところもあり、今後ますます導入されるご家庭は増えていくでしょう。
蓄電池について、こちらの記事で詳しく解説しています。
蓄電池を導入するメリットには以下の4つがあります。
蓄電池のメリットについては、こちらの記事もご覧ください。
蓄電池を導入するデメリットには以下の3つがあります。
蓄電池のデメリットはこちらの記事でも詳しく解説しています。
蓄電池の導入を考えているのなら必ず知っておきたいのが適正価格です。
この適正価格を把握していないと悪徳業者に騙されてしまうこともあります。
蓄電池の適正価格は容量1kWhあたり約15万前後~20万円です。
1kWhあたり20万円以上の高額な見積もりや、反対に10万円などの格安の見積もりを出してくる業者はお断りしましょう。
格安の業者もお断りするのは工事の質が悪い可能性が高いからです。
安物買いの銭失いにならないよう、気をつけましょう。
蓄電池の適正価格についてこちらの記事でより詳しい解説を行っています。

基本的な仕組みは蓄電池も乾電池も同じです。
電池は、電極としてイオン化傾向の異なる2種類の金属(正極・負極)と電解質から構成されています。この3つの化学反応から生まれる電子エネルギーで充放電を行っています。
このうち、正極にはイオン化傾向が小さく電解質に溶けにくい金属が、負極にはイオン化傾向が大きく電解質に溶けやすい金属が用いられます。
リチウムイオン電池の場合、正極にはリチウムの酸化物、負極にはグラファイトなど、電解質には液状かゲル状のリチウム塩の有機電解質が用いられています。
また、両方の電極は層状になっていて、その層の内部にはリチウムイオンを貯めることができます。
電気を充電する場合は、正極の金属が電解質に溶け、その際発生した電子が負極に流れ込み金属化することで充電します。
リチウムイオン電池では、電子の移動と同時にリチウムイオンも正極から負極に移動し、正極と負極の間に電位差を生み出します。この状態が、リチウムイオン電池が充電された状態です。
家庭用蓄電池では、主に単価の安い深夜電力や停電時に太陽光発電で発電した電気を充電します。
電気を放電する場合は、充電とは逆の反応を起こします。つまり、負極側の金属が電解質に溶け、その際に発生した電子が正極側に流れこむことで、電気を放電します。
リチウムイオン電池の場合、電子の移動と同時に正極と負極の電位差を解消することで放電します。この際、正極に戻ったリチウムイオンは電子と結合しリチウム酸化物に還元されます。
家庭用蓄電池では、主に太陽光発電が発電できない夕方以降や雨の日、停電時などに放電をしています。
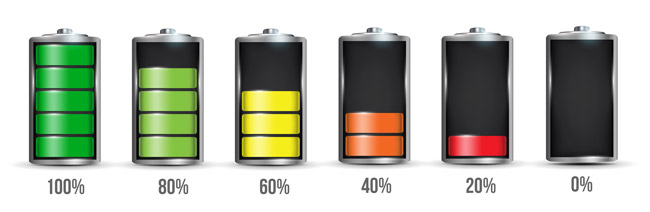
充放電を繰り返すと、蓄電池は徐々に劣化していきます。
リチウムイオン電池もその例に漏れません。
蓄電池には「サイクル寿命」と呼ばれるものがあり、その寿命を過ぎると蓄電容量が減ってしまいます。サイクル寿命については「蓄電池の寿命は何年くらい?サイクル寿命から見る蓄電池の耐用年数」で詳しく解説しています。充放電の仕組みは少々難解な内容でしたが、劣化の仕組みとしては非常に簡単です。
リチウムイオン電池の場合は、充放電によって化学反応を繰り返すことで電池内の正極と負極の金属、リチウムイオン自体が徐々に無くなってしまうことが電池の劣化となります。
劣化が進むと電池自体を交換する必要がありますが、元々の容量の60%程度をサイクル寿命に設定しているメーカーがほとんどなので、すぐに蓄電池が使えなくなるわけではありません。また、家庭用蓄電池に採用されているリチウムイオン電池はサイクル寿命が非常に長く、モバイル用と比べると大きいもので20倍以上の性能差があります。
いかがでしたでしょうか。
普段何気なく使っているスマートフォンなどにも蓄電池が使用されていましたね。現代の生活からは切っても切れないのが蓄電池です。蓄電池を導入するにあたっては、知っている情報が多ければ多いほど正確な判断ができるため、 その仕組みを知っておいて損はありません。
最後に、今回ご紹介した内容をまとめておきます。
「蓄電池駆け込み寺」は、納得の価格と施工であなたのエコな暮らしをサポートします。蓄電池のお見積り・ご相談は駆け込み寺にお任せください!他にも気になる点や、記事にまとめてほしいテーマがあればお気軽にお問い合わせください。
